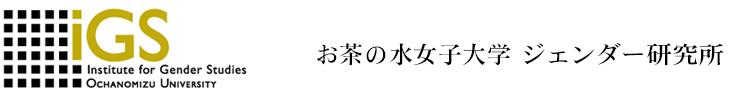IGSセミナー(特別招聘教授プロジェクト)
Millennial Maiko: The Geisha Apprentice in Japanese Popular Culture(ミレニアル舞妓さん:日本のポピュラーカルチャーにおける舞妓像)
2019年2月8日、ジャン・バーズレイIGS特別招聘教授によるIGSセミナー「Millennial Maiko: The Geisha Apprentice in Japanese Popular Culture(ミレニアル舞妓さん:日本のポピュラーカルチャーにおける舞妓像)」が開催された。バーズレイ氏の研究分野は、日本の近現代の女性表象分析である。本セミナーでは、1950年代と2000年代の映像作品に描かれた舞妓像を比較して、舞妓のイメージの変遷をたどった。題材として取り上げられた作品は1953年の映画『祇園囃子』、1955年の映画『ジャンケン娘』、そして2008年のNHK朝の連続テレビ小説『だんだん』である。
21世紀の現在、舞妓は、京都を彩る可愛らしいキャラクターとして人気を集めている。京都で舞妓として働く若い女性の数は75人と決して多くはないが、華やかな着物に日本髪姿の舞妓のイメージは、観光ポスターから舞妓姿のハローキティ人形などのグッズにまで、さまざまな形で描き出され、文化的にも商業的にも、その存在感は大きい。そういった現代の舞妓のイメージの重要な特徴は、身売りや売春といった暗い影がみえないことである。
1950年代の映画作品において、舞妓になることは、経済的な苦境を理由にやむなく選ぶ、生存のための手段である。富裕層の男性の遊興の相手をし、「旦那」というスポンサーに依存する、そして身請けされて愛人か妻となる、つまり「買われる」ことを当然とするのが、花柳界の内外で共有する常識なのだ。踊りやお茶や生花などの技能を高めることは、自分の商品価値を上げることにつながる。
『祇園囃子』では生け花の先生が舞妓たちを、「あなた方も・・・日本の美しさの象徴としての誇りと自尊心を持って毎日勉強するんですよ」と鼓舞する。『ジャンケン娘』では、元芸者の母親が、娘の高校の女性教師の「不潔極まる花柳界」という発言に対し、皮肉たっぷりに反論する。「芸者をまるで家庭の主婦の敵のようにみなさんおっしゃいますけど、どこかに魅力があるんどっしゃろな。旦那さんがお通いになること思いますと。だから私、女がマネていいところはマネてよろしと思います。」舞妓や芸妓が一般女性を上回る女性としての魅力を持つという誇り、より高い価値があるという自信を持つことは、性的商品であることを認めつつも、単なるそれ以上の存在であるという自尊心の表明である。
これに対して2008年のドラマでは、舞妓になることは、「自分らしさ」を追求する過程のキャリア選択のひとつであり、日本舞踊などの伝統芸能の技能を極めるという目標により正当化される。お座敷に来る客は、そこで披露される芸の質を理解する教養のある人たちであり、性的な要素は存在しないかのようである。ドラマに登場する舞妓の祖母である年配女性は、1950年代の映画で描かれているような花柳界のありようを前提に、置き屋もお座敷も穢れた場所だと思い込んでいたが、お座敷で披露された素晴らしい舞を目にして、認識を改める。花柳界のイメージの脱性化を象徴するシーンであり、それは祇園の関係者が望むところであるという。性的な要素が除かれたことにより、ミレニアル世代の舞妓のイメージは、日本のポピュラーカルチャーのキーワードのひとつとも言える「カワイイ」と組みになり、かつて外国人観光客に持て囃された「Geisha」像を脇に押しやって、京都のイメージ・キャラクターになったのだ。
研究報告に続く質疑応答では、多くの質問やコメントが出され、時間を延長して議論が続けられた。本セミナーは、参加者にとって知的刺激の多いものとなった様子であった。バーズレイ氏は、本報告内容を含む舞妓研究の成果をまとめた書籍を執筆中で、この場での議論が原稿の内容を充実させることに繋がったという。その書籍の刊行がとても楽しみである。
記録担当:吉原公美(IGS特任リサーチフェロー)


《開催詳細》
【日時】2019年2月8日(金)14:30〜16:00
【会場】本館125室
【報告者】ジャン・バーズレイ(IGS特別招聘教授/ノースカロライナ大学チャペルヒル校教授)
【主催】ジェンダー研究所
【言語】英語
【参加者数】20名