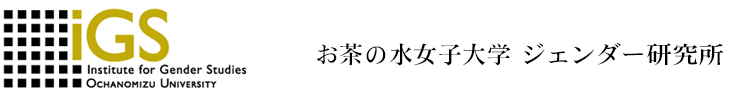IGSセミナー報告「立ち位置を理解する:日本の新宗教フィールドワークからの考察」
リフレクションや立ち位置の課題については、70年代から継続的に議論されているが、現在、そして以降も常に研究者が向き合い、考え続けなくてはいけない課題といえる。そしてそれは、文化人類学やエスノグラフィー分野に限らず、社会学や開発学ほか、様々な分野の研究現場においても考察されている。
インタビューや参与観察を伴うフィールドワークでは、研究者の個性、性別、セクシュアリティや人生経験が、調査の様々な局面に影響する可能性がある。例えば、バッフェッリ氏の場合、インタビュー相手や、調査対象団体の窓口となるインフォーマントとの出会いの場で、会話の糸口となったのは、音楽の趣味や、同じ地域に居住したことや、出産・育児などの共通する経験であったりするという。また、特に女性の元オウム真理教信者へのインタビューの際には、同じ女性であることが、話しやすい相手と思われることに役立っているのではと感じているそうだ。ある程度の親しさ、近さに身を置けるということが、インタビューをうまく進める必須条件となる。
そうした面があるだけに、研究対象との距離の置き方には、十分な配慮が必要である。例えば、宗教団体との関係では、参与観察を続ける条件として入信を迫られる場面もあるという。また、団体が自分たちを調査対象としている研究者を、公的承認の証として利用しようとすることもある。また、宗教団体または信者グループには、メンバー以外には明かさない秘密の部分が必ず存在する。このような、調査の限界に面した際には、研究者としての目的は何かを自分の中で明確にして、行動方針を決めなくてはいけない。
こうしたことから、研究者は、フィールドにおいて、自分は何者なのか、自分の中のどの部分を仕事や研究に使っているのかの自問自答を経験することになる。研究者間で広く理解されるようになっているのは、研究者は見えない存在なのではないということだ。そして、研究者自身の個性がフィールドワークに影響することは無視できない。個性は、インタビューを円滑に進めるなど有利に働く場合もあれば、女性であるということが身体的危険につながるなど不利に働く場合もある。つまりは、研究に自己が反映される可能性があるといえる。
また、フィールドワークには、人との出会いや関係づくりが必須であることから、研究者がフィールド社会やその人間関係に介入することに伴うリスクが存在する。研究者はいつでもフィールドを去ることができるが、研究対象者はそうではないという面もあり、自分が与える影響についての熟慮が必要である。前出の研究対象との接触が自己に内省を促す点と、この自己が研究対象に与える影響とを合わせ、フィールドワークは、双方向の影響(リフレクション)とその循環を生み出すと言える。
また、エスノグラフィーにおける研究者と研究対象者との力関係は、対等ではない。フィールドワークそのものは、研究者と研究対象者の協働作業により成り立つものだが、それを論文として公表する作業は研究者の手に委ねられることになる。誰の「声」がそこに書かれているのかは、両者間の力関係の表れであり、また、研究者の立ち位置を示すものにもなる。
立ち位置の問題についての議論は、西洋中心主義的なステレオタイピングを避けるべきという議論から始まった。議論の流れを受けて、最近は、文化人類学者の文章に、自分は「これこれの」立場からこれを書いているといった断り書きが登場するようになっているという。これが極端に高じると、研究者が自分自身を、人種や階級、文化背景に基づくカテゴリーに自分を閉じ込めてしまうセルフ・ステレオタイピングを生じさせる危険性がある。フィールドワーク現場で起こる研究者自身へのリフレクションが、アイデンティティの認識を強めさせるが故のことでもある。しかし、既存の型通りの属性に自らを当てはめることは、個々の研究者の個性を埋没させ、かつ、研究対象者と自らの属性の対比によるステレオタイピングをももたらしてしまう可能性がある。
バッフェッリ氏が自身の研究について語る中で、立ち位置の問題に関し、よく耳にするエスノグラファーの体験とは異なり、調査対象者のグループは自身とは異なる価値観を持つ人々で、その話に共感を抱くということはまずないと話している。しかし同時に、調査しているのは宗教団体で、その構成員である彼ら、彼女らは、同じ価値観や世界観、宗教的指導者を持つ人々ではあるが、団体を均一な人々の集団とは見ずに、その中の多様性に目を向け、集団ではなく、個人個人として接するようにしているという。話を聴きながら、時にはその内容を不快に思うこともあるが、調査対象者の中に自分と近い部分を感じたりすることもあるという。例えば、比較的若い元オウム真理教信者は、自分と同世代で、同じ時代に学校に通い、同じポピュラーカルチャーに親しみ、同じ本を読んだり、同じような疑問を抱いたりしてきている。この点について、バッフェッリ氏は、ジュディス・バトラー著『自分自身を説明すること』(月曜社、2008年)から、たとえ非難の対象とする相手であっても、その相手との近しさや関係の形成抜きでは、倫理的な判断をすることはできない、と述べられている一節を紹介した。
講義の冒頭で、バッフェッリ氏は、フィールドワークとは他者との出会いであると説明しているが、それは、単なる点での遭遇ではない。互いの背景にある歴史や経験、体験や思い出を語るという行為、リフレクションによる相互作用や内省、そしてフィールドワーク後に行われるデータの分析・考察などを通して、「関係」が形成される。このため、研究者の立ち位置も、初めから確固たる点として決定できるものではなく、様々な相互作用を経ながら設定される部分があるだろう。研究は、他者についての何らかの「判断」をすることでもあるが、そのための考察をより深く豊かな人間性への理解に導くのは、この「関係」についての理解なのだと言える。
この他にも、インターネットを含むメディアを活用したエスノグラフィーや、新たに取り組んでいる研究プロジェクト「女性、宗教、暴力」についてなど、バッフェッリ氏の研究内容の紹介もあった。研究者としてのスタートから最近の研究活動まで網羅し、かつリフレクションや立ち位置といった、フィールドワークの主要課題に焦点を当てたバッフェリ氏の語りは、研究に対する熱意のみならず、研究者としてのプロフェッショナリズムをも感じさせるものであった。
記録担当:吉原公美(IGS特任RF)
 エリカ・バッフェッリ氏
エリカ・バッフェッリ氏

【日時】2016年12月14日(水)13:00~14:30
【会場】お茶の水女子大学本館124室
【講師】Erica Baffelli(IGS特別招聘教授、マンチェスター大学准教授)
【主催】お茶の水女子大学ジェンダー研究所
【参加者数】10名